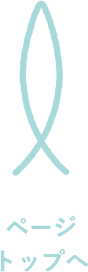【インタビュー記事】Ocean at Risk 02「北極海の海氷融解」川口悠介
北極海の海氷融解が急速に拡大 海洋大循環の乱れとポーラーロウの多発を誘引
過去35年間で夏季の海氷面積が3分の2程度に減少したとされる北極海の「海氷」。温暖化などの影響で融解は急速に拡大しており、海洋や気象そして生態系に多大な影響がおよんでいる。海洋物理学の視点から北極海の海氷とその融解のメカニズムを知ることで、海に迫る危機をより深く学ぶことができる。
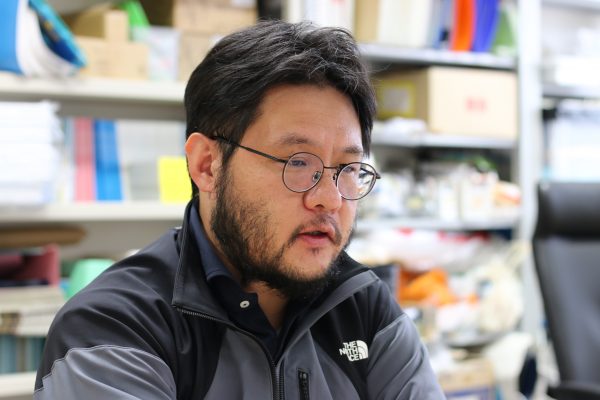
地球の極域である北極と南極はそれぞれ氷に覆われていますが、このふたつにはどのような違いがあるのでしょうか。
川口悠介|南極の氷は南極大陸の上に降り積もった雪によって形成された「氷床」と呼ばれるもので、その厚さは数千mにおよびます。他方、北極の氷は海水が凍ったもので「海氷」と呼ばれます。北極海の水深が3000mほどなのに対して、海氷の厚みは2mに満たない程度しかありません。
北極海の海氷はどのように生成されるのですか。
川口|北極海には太平洋からベーリング海峡を経て海水が流入しており、海氷は海面がマイナス 15°Cくらいになったときに生成されます。そして、北極海の中央海盆域で生成された海氷は東グリーンランド海流に乗って南に移動し、ノルウェー海や大西洋に流出、温暖な中緯度の海域まで流れ着く過程で融かされていきます。北極海の中央起源の氷が融けるまでにかかる時間は、およそ2〜3年といったところです。また、カナダの北部でも海氷は生成されますが、それらは 1 年ほどで大西洋のほうに移動し融けてしまいます。ちなみに、現時点で北極点の周辺は 1 年をとおして氷に覆われていますが、そのほかのエリアについては季節によって変動があります。もちろん、その面積は夏場に最小になり、冬場に最大になります。
北極海の海氷が少なくなってきているという話がありますが、実際にはどうなのでしょうか。
川口|大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所(極地研)と国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)による北極海の海氷観測研究によると、北極海の海氷面積が2019年9月17日に396万km2と年間最小値を記録したことが判明しました。この面積は 2019年の最小値であるとともに、人工衛星による観測史上、2012年につぐ2番目の小ささです。しかも、過去35 年間で夏季の海氷面積が3分の2程度に減少しているというデータもあります。原因は諸説ありますが、ベーリング海峡から流入する海水温が高くなり、氷の生成量が減少したことなどが指摘されています。
以降については、こちらからご覧いただけます。