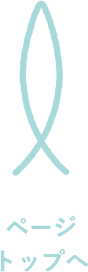【インタビュー記事】Ocean at Risk 05「海洋ごみと騒音」青木かがり
バイオロギングで明らかになりつつある海洋プラスチックごみと海中騒音の影響
野生動物に記録装置を取り付けることで、その行動を明らかにするバイオロギングという研究手法がある。近年はこの手法によって海洋動物の行動はもちろん、海洋プラスチックごみや海中騒音が動物に与える影響も明らかになってきている。これからはそういった研究成果をもとに、いかに海洋動物を守っていくかを考え、行動していかなければならない。

まず青木先生が取り組んでいるバイオロギングについて教えてもらえますか。
青木かがり|バイオロギングとは野生動物に直接、小型の記録装置を取り付け、動物の行動や暮らしている環境などを調べる手法のことです。野生動物の生態、とくになかなか追うことができない海洋動物の生態は未知の部分が多く、バイオロギングは非常に有効な研究方法と言えます。ちなみに、このバイオロギングという言葉は日本で誕生しました。手法そのものは1960年代にアメリカのジェラルド・クーイマン博士がキッチンタイマーを改良した記録装置をアザラシに付けたところからスタートしたのですが、2003 年に第1回国際シンポジウムを日本で開催した際、大会組織委員会がバイオロギング(Bio-Logging)と名付けたのです。
具体的にはどのようなことがわかるようになったのでしょうか。
青木|クジラに関しては、20 年ほど前からバイオロギングによる調査が実施され、最近で はビデオカメラや行動記録計を搭載した記録装置を付けることで、クジラが海中でどのよ うな生活を送っているかがより明確にわかるようになってきました。たとえば、バイオロギングによってヒレナガゴンドウはお猿さんの毛づくろいと同じように体を触れ合わせることがわかってきました。ヒレナガゴンドウは、頭はずんぐりと丸く、イルカと違って吻(ふん)は出ておらず正面から見るとまるで笑っているかのように見える愛嬌のある顔立ちのクジラです。彼らは群れで生活しており、ヒレナガゴンドウ 1 頭に行動記録計を、もう一頭に動物カメラを取り付けたところ、2 頭のヒレナガゴンドウは、ぴったりと息を合わせて同調して泳いでいることが分かりました。その間、ときおりお互いの体をさわりあったり、胸びれで体をゴシゴシこすったりしていました。霊長類にみられる社会的グルーミングと同じように、ヒレナガゴンドウもお互いのからだを触り合うことで、互いのきずなを深めているのかもしれません。
以降については、こちらからご覧いただけます。