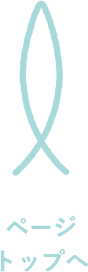【インタビュー記事】Ocean at Risk 07「サンゴの白化」茅根創
地球温暖化と海洋酸性化によって地球規模で深刻化するサンゴの白化
2000年代に入って、地球規模でのサンゴの白化が頻繁に発生している。2016〜2017年にかけてはグレートバリアリーフ(オーストラリア)を形成する半分以上のサンゴが白化するというショッキングな現象も発生した。その原因やメカニズムを学びつつ、どうすればこの現象に歯止めをかけることができるのかを考えていきたい。

まずサンゴという生物の特徴についてお聞かせください。
茅根創|サンゴはイソギンチャクやクラゲと同じ刺胞動物の仲間であり、それらの生物と同じように触手を持ち、動物プランクトンなどを刺して摂食します。また、石灰質の骨格を形成する造礁サンゴの骨格のなかには褐虫藻が生息しており、光合成系による共生(褐虫藻が光合成でつくった有機物をサンゴが摂取する)を成立させています。そのほかにも、サンゴは海洋中でさまざまな役割をはたしています。たとえば、造礁サンゴの石灰質骨格が積み重なって造るサンゴ礁は天然の防波堤になっていますし、褐虫藻の光合成産物がサンゴを経由して生物の餌になるとともに、複雑な骨格が多くの棲み処にもなるため、サンゴ礁は海洋でもっとも生物多様性が高い海になっています。
地球温暖化によるサンゴの白化はいつ頃から発生しているのでしょうか。
茅根|地球規模でサンゴの白化が初めて観測されたのは1998年のことで、主な原因はエルニーニョ現象による海水温の上昇とされています。そして、それ以降もサンゴの白化は世界各地で発生しつづけています。2003〜2010年にかけて何回か大規模な白化が発生しましたし、2016〜2017年には世界最大のサンゴ礁地帯であるオーストラリアのグレートバリアリーフが700kmにわたって白化し、全体の半分以上がダメージを受けてしまいました。
日本でもサンゴの白化は発生しているのですか。
茅根|日本でも2016年に石垣島から西表島の間に広がる石西礁湖と呼ばれるサンゴ礁において、約8割が白化するという深刻な事態が生じています。
以降については、こちらからご覧いただけます。